共働き家庭にとって、子どもの教育環境選びは大きな課題です。特に共働きでありながら私立小学校に希望する方は、仕事と育児を両立しやすい学校を探しているのではないでしょうか。私立小学校は教育環境が整っている一方で、通学の付き添いや親の関与が求められる場面もあり、共働き家庭が不利に感じることがあります。
しかし、最近では共働きが多い私立小学校も増え、東京を中心にアフタースクールやシッターサービスが充実した学校も多く見られます。放課後や夏休みのサポート体制が整っていれば、仕事と育児の両立も可能です。
この記事では、共働き家庭におすすめの私立小学校の選び方やサポート体制について詳しく紹介します。
- 共働き家庭におすすめの私立小学校の特徴
- 共働き家庭が小学校受験で直面する課題と対策
- 東京で共働きに優しい私立小学校の選び方
- 放課後や夏休みに活用できるサポート体制
共働き家庭におすすめな私立小学校の選び方
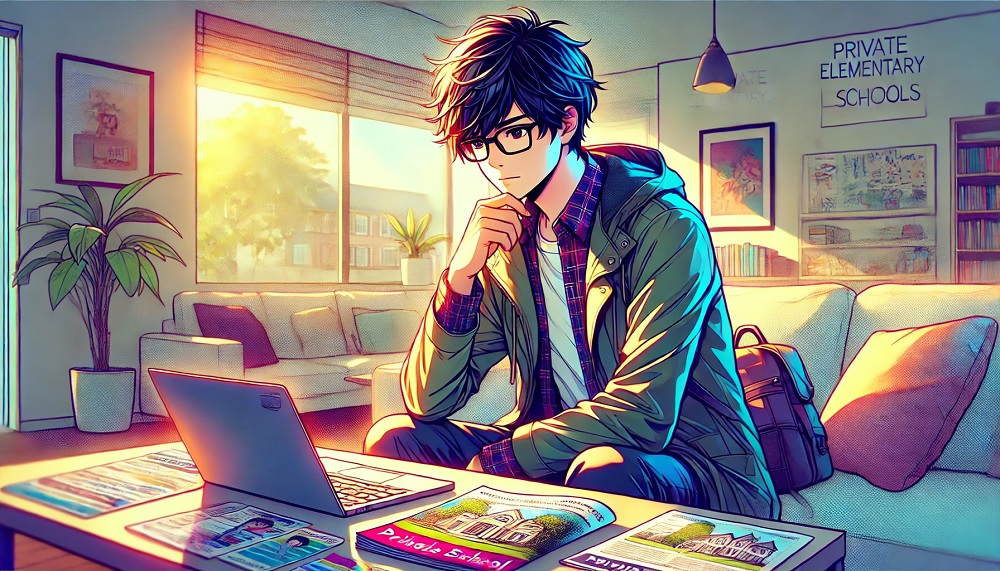
- 小学校受験で共働きが不利と言われる理由
- 共働きが多い私立小学校の特徴
- 共働き家庭に優しい東京の私立小学校
- 母親が仕事と両立するコツ
- 共働き家庭向けアフタースクールの充実度
小学校受験で共働きが不利と言われる理由
小学校受験において、共働き家庭は「不利」と言われることがあります。これは単なる噂ではなく、受験の準備や当日の対応など、共働きならではの課題が背景にあるからです。
まず、共働き家庭が直面する最大の課題は「時間の確保」です。小学校受験は親子で取り組むものとされており、受験準備には相当な時間が必要です。幼児教室への通塾、家庭学習、課題の提出、模試の受験など、平日・週末問わず予定が埋まります。このスケジュールをこなすには、少なくとも片方の親がある程度時間を割ける環境が理想です。しかし共働きの場合、仕事の都合で子どもの送迎やサポートが十分にできないことがあります。
また、小学校受験では「親の関与」が重視される場面もあります。例えば、面接では「家庭の教育方針」や「子どもへの関わり方」について質問されることが多いです。このとき、共働き家庭の場合、「子どもと過ごす時間が少ないのでは?」と懸念されることがあります。特に専業主婦の家庭が多い学校では、共働き家庭に対して「受験後の学校生活をサポートできるのか」といった視点で見られることもあるでしょう。
さらに、保護者参加型の行事が多い学校では、共働き家庭にとって負担が増える可能性があります。説明会や学校見学は平日に行われることが多く、仕事を調整して参加する必要があります。また、面接日程も学校側が指定するため、仕事との両立が難しくなることがあります。
しかし、これらの課題を理解したうえで対策を講じれば、共働き家庭でも十分に小学校受験を成功させることが可能です。具体的には、夫婦で役割を分担し、スケジュールを徹底的に管理することが重要です。また、学校選びの際には「共働き家庭に理解のある学校」を選ぶことも一つの方法です。最近では、共働き家庭が増加していることもあり、柔軟な対応をしてくれる学校も増えています。
共働きが多い私立小学校の特徴

共働き家庭が多く通う私立小学校には、いくつかの共通した特徴があります。これらの学校は、忙しい保護者のニーズに応えるための工夫が施されており、共働き家庭にとって通いやすい環境が整っています。
まず、最も大きな特徴として「アフタースクール(学童保育)」の充実があります。放課後の時間を有意義に過ごせるよう、多くの学校ではアフタースクールを用意しており、最長で19時まで預かってくれるところもあります。このアフタースクールでは、宿題のサポートや習い事の時間が設けられており、共働き家庭の保護者にとって非常に心強い存在です。例えば、英語、プログラミング、スポーツなど、さまざまなカリキュラムが組まれていることもあり、放課後の時間を有意義に活用できます。
次に「給食制度の充実」も重要なポイントです。共働き家庭にとって、毎日のお弁当作りは大きな負担です。そのため、週5日給食が提供される学校や、校内で温かい食事を提供する食堂がある学校は、共働き家庭から特に人気があります。食事面での負担が減ることで、保護者は仕事に集中しやすくなります。
また「保護者の負担を軽減する学校行事」も特徴の一つです。保護者参加型のイベントを最小限に抑えたり、平日の行事をオンラインで配信するなど、共働き家庭に配慮した取り組みを行っている学校も増えています。PTA活動への参加を強制しない学校や、役員活動を希望制にしている学校も多く、忙しい共働き家庭でも無理なく学校生活をサポートできる環境が整っています。
さらに「通学の安全性」も共働き家庭が重視するポイントです。共働き家庭の子どもは自宅から学校まで一人で通学することも多いため、スクールバスが完備されている学校や、登下校時に教師や地域の方が見守ってくれる「登下校サポートシステム」がある学校は人気です。通学路の安全が確保されていれば、親も安心して送り出せます。
このように、共働き家庭が多い私立小学校には、保護者の負担を減らしながら子どもの教育環境を整える工夫が多数取り入れられています。これらの特徴を踏まえて学校選びをすることで、共働き家庭でも無理なく私立小学校に通わせることができるでしょう。
共働き家庭に優しい東京の私立小学校

東京には共働き家庭に優しい私立小学校が多く存在し、忙しい保護者でも安心して子どもを通わせられる環境が整っています。これらの学校では、学業だけでなく、共働き家庭のライフスタイルに配慮した制度が充実しているのが特徴です。
例えば「東京農業大学稲花小学校」は、共働き家庭に非常に配慮された私立小学校です。この学校では週5日の給食提供に加え、最長で19時まで利用できるアフタースクールが設置されています。また、Zoomを活用したオンライン授業参観なども実施しており、仕事の合間に子どもの学校生活を見守ることができます。さらに、PTAの負担を軽減するための取り組みも行っており、役員活動を希望制とすることで、共働き家庭でも無理なく学校運営に関わることが可能です。
また「日本女子大学附属豊明小学校」も共働き家庭に優しい私立小学校として知られています。この学校では、女子校で初めてアフタースクールを導入し、働く保護者のニーズに応えています。内部進学率も高く、将来的に中学受験を回避したいと考える家庭にとっても魅力的です。加えて、学校独自の教育プログラムも充実しており、学業と社会性の両立を図ることができます。
「江戸川学園取手小学校」も共働き家庭から高い評価を得ています。この学校のアフタースクールは非常に充実しており、学習サポートだけでなく、英語、スポーツ、アートなど幅広い講座を提供しています。さらに、ほぼ全員が併設中学校に進学するため、中学受験の負担を軽減できる点も魅力の一つです。学校行事やPTAの負担も比較的軽いため、共働き家庭でも無理なく参加できる環境が整っています。
東京の共働き家庭に優しい私立小学校を選ぶ際には、「アフタースクールの充実度」「給食の有無」「保護者負担の軽減策」などを基準にするとよいでしょう。これらの条件を満たす学校であれば、共働き家庭でも子どもの教育と仕事の両立が可能になります。また、学校見学や説明会に参加して、実際の環境や雰囲気を確認することも重要です。
このように、東京には共働き家庭に配慮した私立小学校が多く存在します。家庭のライフスタイルや価値観に合った学校を選ぶことで、親も子どもも安心して学校生活を送ることができるでしょう。
母親が仕事と両立するコツ

共働き家庭で小学校受験を目指す場合、母親が仕事と育児を両立するのは大きな課題となります。時間的な制約が多い中で、効率よく準備を進めるには、いくつかの工夫が必要です。
まず重要なのは、スケジュール管理の徹底です。小学校受験の準備には、幼児教室への通塾、家庭学習、模試の受験など、多くの予定が発生します。これらを仕事と両立させるためには、家族全員で予定を共有し、無駄な時間を減らすことが大切です。Googleカレンダーなどの共有アプリを使い、夫婦で送迎や学習のスケジュールを管理すると、急な予定変更にも対応しやすくなります。また、1週間単位で予定を立て、週末には夫婦でミーティングをして、翌週の予定を確認するのも効果的です。
次に、家事の効率化と外注化も大きなポイントです。共働きの場合、仕事と受験準備に加え、日々の家事をこなすのは非常に負担が大きくなります。そこで、家事代行サービスや食材宅配サービスなどを活用し、家事の負担を軽減しましょう。例えば、週末に作り置きの食事を準備することで、平日の夕食作りの時間を短縮できます。また、掃除や洗濯などの家事を家族で分担することも大切です。家族全員で協力し、母親だけに負担が偏らないように工夫しましょう。
時間の「見える化」も有効な手段です。仕事、家事、育児、受験準備のそれぞれにどれだけの時間を使っているのかを可視化することで、無駄な時間を発見できます。たとえば、通勤時間を短縮するために在宅勤務を導入したり、朝の時間を活用して家庭学習を進めるといった工夫が可能です。特に朝の時間は集中力が高いので、子どもの勉強に最適な時間帯と言えます。
また、自分自身のリフレッシュの時間も忘れてはいけません。受験準備は長期戦ですので、母親自身が心身ともに健康を保つことが大切です。週に1回でも自分の趣味や好きなことに時間を使うことで、ストレスを軽減でき、気持ちに余裕が生まれます。リフレッシュすることで、子どもへの接し方にも余裕が生まれ、より良い親子関係を築けるでしょう。
最後に、完璧を求めすぎないことも重要です。共働きで小学校受験に挑む家庭にとって、すべてを完璧にこなすのは現実的ではありません。時には「今日はここまでで十分」と割り切ることも必要です。また、周囲のサポートを積極的に受け入れることも大切です。祖父母やシッターサービスの協力を得ることで、負担を大きく軽減できます。
このように、スケジュール管理や家事の効率化、周囲の協力を活用することで、母親が仕事と育児、そして小学校受験の準備を両立することは十分可能です。無理をせず、自分に合った方法を見つけながら、家族全員で乗り越えることが成功のカギとなります。
共働き家庭向けアフタースクールの充実度

共働き家庭にとって、アフタースクール(学童保育)の充実度は、私立小学校選びの大きなポイントになります。放課後の時間を有意義に過ごせる環境が整っていれば、保護者の負担を軽減できるだけでなく、子どもの成長にもつながります。
まず、基本的なアフタースクールの役割は、放課後の子どもを安全な環境で預かることです。しかし、近年の私立小学校では、単なる預かりではなく、学習や習い事を含む多彩なプログラムを提供するアフタースクールが増えています。例えば、英語やプログラミング、音楽、スポーツなど、子どもの興味や特技を伸ばせるプログラムが組み込まれていることが多く、放課後の時間を有意義に活用できます。
また、宿題サポートや学習支援が充実しているアフタースクールも多くあります。共働き家庭では、夕方以降に帰宅した後に宿題を見てあげる時間が限られるため、アフタースクールで宿題を終わらせてくれると、家庭での負担が大幅に軽減されます。さらに、基礎学力を補強する学習講座や、中学受験を見据えた特別クラスを設けている学校もあり、放課後の時間を活用して学力アップを図ることができます。
送迎サービスの有無も、共働き家庭にとって重要なポイントです。特に低学年のうちは、学校からアフタースクールまでの移動に不安を感じる保護者も多いでしょう。そのため、学校内にアフタースクールが併設されている場合や、学校からアフタースクールまでスタッフが送迎してくれるサービスは非常に便利です。また、一部のアフタースクールでは、自宅や最寄り駅まで送迎してくれるサービスもあり、仕事で帰宅が遅くなる保護者にとって心強い存在です。
長期休暇中の対応も、アフタースクール選びで見逃せないポイントです。夏休みや冬休みなどの長期休暇中に、朝から夕方まで預かってくれるプログラムがあるかどうか確認しましょう。一部のアフタースクールでは、サマースクールや特別講座を開催し、子どもが楽しみながら学べる機会を提供しています。例えば、理科実験教室や英語キャンプ、アートワークショップなど、多彩な体験型プログラムが組まれていることもあります。
また、アフタースクールの費用も考慮する必要があります。私立小学校に併設されているアフタースクールの場合、1時間あたり数百円から利用できるところが多いですが、民間の学童保育に比べて割高なケースもあります。月額制やチケット制など、利用形態もさまざまなので、自宅の経済状況に合わせて無理のない範囲で選ぶことが大切です。
このように、共働き家庭向けのアフタースクールは、単なる預かり場所以上の価値を提供しています。学習支援や習い事、送迎サービス、長期休暇中のプログラムなど、子どもの成長をサポートしつつ、保護者の負担を軽減できる環境が整っています。学校選びの際には、これらのアフタースクールの充実度をしっかりと確認し、家族のライフスタイルに合った環境を選ぶことが重要です。
私立小学校を目指す共働き家庭におすすめなポイント

- 放課後の過ごし方に悩む家庭は多い
- 夏休みも安心できる学童やサマースクール
- 通学に付き添いが必要な場合の注意点
- 送迎でシッターを活用した放課後サポート
- 私立小学校に通う世帯年収と学費の実態
放課後の過ごし方に悩む家庭は多い
小学校入学後、多くの共働き家庭が直面するのが「放課後の過ごし方」に関する問題です。特に私立小学校の場合、公立小学校よりも授業終了が早いことが多く、子どもが自宅で一人の時間を過ごさなければならないケースがあります。このような状況に不安を感じる家庭は少なくありません。
まず、放課後の時間帯は子どもにとって非常に重要な成長の機会です。宿題を終わらせるだけでなく、遊びや習い事を通じて社会性や創造性を育む大切な時間でもあります。しかし、共働き家庭では親が仕事から帰宅するまでの数時間、子どもがどう過ごすかが大きな課題となります。一人で過ごす場合、ゲームやテレビの時間が増えてしまい、生活リズムが乱れることもあります。また、安全面の心配も大きな問題です。
このような背景から、多くの家庭では放課後の預かり施設やアフタースクールを活用しています。アフタースクールでは、宿題のサポートだけでなく、英語、プログラミング、スポーツなど多彩なカリキュラムが用意されていることが多く、放課後の時間を有意義に過ごせます。さらに、友達と一緒に過ごせることで、社交性の向上にもつながります。
ただし、すべての家庭がアフタースクールを利用できるわけではありません。費用の問題や、近隣に適切な施設がない場合もあります。また、子ども自身が放課後に習い事を複数掛け持ちしたり、自宅で静かに過ごしたいと希望することもあります。このような場合には、在宅ワークやフレックスタイム制度を活用し、保護者が柔軟に対応できる環境を整えることが求められます。
放課後の過ごし方に悩む家庭は多いものの、重要なのは「子どもが安心して楽しく過ごせる環境」を整えることです。家庭のライフスタイルや子どもの性格に合った方法を見つけることで、放課後の時間を有意義なものにできるでしょう。
夏休みも安心できる学童やサマースクール

共働き家庭にとって、夏休みの過ごし方は大きな課題です。学校が長期休暇に入る一方で、親は通常通り仕事があるため、子どもをどこに預けるか悩むケースが多くあります。このため、夏休み中も安心して子どもを預けられる学童やサマースクールの利用が注目されています。
まず、学童保育は夏休み期間中も利用できる場合が多く、特に共働き家庭には強い味方です。公立の学童では基本的な見守りが中心ですが、私立小学校に併設されているアフタースクールや民間学童では、夏休み期間中に特別なプログラムを提供していることがあります。例えば、理科実験教室やスポーツ大会、工作教室など、通常の学童保育にはない体験型のプログラムが実施され、子どもたちにとって貴重な学びの場となります。
一方、サマースクールは、夏休みならではの特別なプログラムを提供する施設です。特にインターナショナルスクールや語学学校が主催するサマースクールでは、英語での授業や異文化交流を体験できるプログラムが人気です。9時から15時半までのスケジュールで、遊びと学びがバランスよく組み込まれています。また、同じ私立小学校に通う子どもたちが参加していることも多く、友達と一緒に楽しく過ごせる点も魅力です。
さらに、スポーツや文化活動のキャンプも夏休みの選択肢の一つです。スイミング、サッカー、バスケットボールなどのスポーツキャンプや、音楽、絵画、プログラミングといった学びのキャンプも多く開催されています。これらのキャンプでは、特定のスキルを集中的に学べるだけでなく、同年代の子どもたちと協力しながら活動することで、社会性や協調性を育むこともできます。
ただし、夏休みの学童やサマースクールを選ぶ際には、いくつかの注意点があります。まず、定員に限りがあることが多く、人気のプログラムはすぐに埋まってしまいます。そのため、早めに申し込みを済ませることが重要です。また、費用の確認も大切です。特に私立のサマースクールや専門的なキャンプは費用が高額になる場合がありますので、家計と相談しながら選ぶ必要があります。
| 項目 | 公立学童保育 | 民間学童保育 | サマースクール |
|---|---|---|---|
| 利用時間 | 8:00~18:00 | 7:30~20:00 | 9:00~15:30 |
| 費用(1か月あたり) | 約5,000円~10,000円 | 約40,000円~80,000円 | 約50,000円~100,000円 |
| 提供プログラム | 基本的な遊び中心 | 学習+習い事併設 | 英語・プログラミング・スポーツなど |
| 食事提供 | お弁当持参(地域差) | 軽食やお弁当提供あり | お弁当持参・一部提供 |
| 送迎サービス | なし | あり | 一部あり |
このように、夏休み期間中も学びと遊びをバランスよく取り入れたプログラムを活用することで、共働き家庭でも安心して子どもを預けることができます。親も安心して仕事に専念でき、子どもも楽しく有意義な夏休みを過ごせるため、積極的に活用していきましょう。
通学に付き添いが必要な場合の注意点

私立小学校に通う場合、特に低学年のうちは親が通学に付き添うケースが多く見られます。公共交通機関を利用して通学することが一般的な私立小学校では、安全面や生活リズムの管理が重要な課題です。ここでは、通学に付き添う際の注意点について詳しく解説します。
まず、最も重要なのは安全面の配慮です。特に1年生の4月からの数週間は、登下校の際に親が完全に付き添うことが一般的です。公共交通機関を利用する場合、混雑する時間帯を避けるルートを選ぶことが推奨されます。また、子どもが電車やバスの乗り降りに慣れるまで、改札の出入りや座席の確保などのサポートが必要です。電車内でのマナーや危険な行動についても、実際の通学中に教えると効果的です。
次に、段階的な自立の促進も重要なポイントです。入学後すぐに一人で通学するのは難しいため、段階を踏んで自立を促すことが大切です。例えば、最初の1週間は学校まで付き添い、2週目からは最寄り駅まで、3週目からは乗り換えの駅までと、少しずつ距離を伸ばしていきます。この方法により、子どもが自信を持って一人で通学できるようになります。
さらに、通学路の確認と緊急時の対応についても事前に話し合っておきましょう。通学路に危険な箇所がないか確認し、子どもと一緒に歩いて安全なルートを選びます。また、もし迷子になったり、電車が遅延したりした場合の対応策も教えておくと安心です。親の連絡先を記載したカードを持たせたり、携帯電話を持たせるのも一つの方法です。
共働き家庭の場合、通学の付き添いが難しいこともあります。この場合、信頼できるシッターサービスを利用するのも一つの選択肢です。シッターが自宅から学校までの送迎を担当してくれるサービスもあり、共働き家庭の強い味方となっています。また、同じ学校に通う家庭と協力して、交代で登下校の見守りを行う「登校班」のような仕組みを作ることも効果的です。
最後に、子どもの精神的なサポートも忘れてはいけません。新しい環境での通学は、子どもにとって大きなストレスになることがあります。無理に自立を急がせるのではなく、子どものペースに合わせて少しずつ慣れさせることが大切です。通学中に不安や怖い思いをしていないか、定期的に子どもと話し合い、不安を取り除いてあげましょう。
このように、通学に付き添う際には安全面や段階的な自立を意識しながら、子どもの心身の負担を軽減する工夫が必要です。家庭の状況に応じて、シッターサービスや近所のサポートを活用することで、共働き家庭でも安心して通学を見守ることができるでしょう。
送迎でシッターを活用した放課後サポート

共働き家庭にとって、子どもの放課後の過ごし方は大きな課題の一つです。特に私立小学校に通う場合、学校の終業時間が早かったり、アフタースクールの終了時間と保護者の仕事終わりが合わないことが多くあります。こうした状況の中で、送迎を含めたシッターサービスの活用は、共働き家庭にとって非常に有効なサポート手段となっています。
まず、シッターサービスの大きな魅力は、柔軟な対応力にあります。例えば、学校の終業後にシッターが直接お迎えに行き、自宅までの送迎を行うサービスがあります。この場合、保護者が仕事を終えるまでの数時間、自宅でシッターが子どもを見守りながら、宿題や軽い学習のサポート、遊び相手をしてくれることが一般的です。このようなサービスを利用すれば、親が帰宅するまで子どもが安全かつ有意義な時間を過ごすことができます。
また、習い事への送迎を含むシッターサービスも人気があります。多くの子どもが放課後に習い事をしているため、シッターが学校から直接習い事の場所まで送迎し、終了後に自宅へ連れて帰るといった利用方法も可能です。このようなサポートがあれば、親が直接送り迎えをする必要がなくなり、仕事に集中できる時間が増えるため、共働き家庭には大きな助けとなります。
安全性の確保もシッターサービスを選ぶ際に重要なポイントです。信頼できるシッターサービスは、スタッフの研修や身元確認を徹底しており、送迎中のトラブルを避けるためのガイドラインを設けています。また、GPSを利用してシッターと子どもの現在地をリアルタイムで確認できるサービスも増えており、保護者が安心して任せられる環境が整っています。
一方で、シッターサービスを活用する際には、いくつかの注意点があります。まず、費用の確認です。シッターサービスは1時間あたり2,000円~3,000円程度が相場ですが、送迎を含む場合は追加料金がかかることもあります。また、夕方のピークタイムには予約が取りづらくなることもあるため、早めのスケジューリングが必要です。さらに、シッターとの相性も大切な要素です。子どもがシッターに安心して接することができるかどうかを確認するために、初回は短時間の利用から始めるとよいでしょう。
最後に、シッターサービスを活用するメリットとして、子どもの成長に合わせたサポートができることが挙げられます。単なる送迎だけでなく、英語やピアノなど特定のスキルを持つシッターを選べば、放課後の時間を有効活用し、習い事のような形で学びの機会を提供することも可能です。
このように、送迎を含むシッターサービスは、共働き家庭の放課後サポートとして非常に有効な手段です。安全性や費用、子どもとの相性を考慮しながら、自宅のライフスタイルに合ったシッターを見つけることで、親も子どももストレスの少ない放課後を過ごせるようになります。
私立小学校に通う世帯年収と学費の実態

私立小学校への進学を考える際、多くの家庭が最も気になるのが「学費」と「必要な世帯年収」です。公立小学校と比較して、私立小学校は授業料や諸費用が高額であることが一般的です。ここでは、私立小学校にかかる学費の実態と、それに見合った世帯年収の目安について詳しく解説します。
まず、私立小学校にかかる年間の学費についてですが、文部科学省の調査によると、1年間にかかる学習費総額は約166万円とされています。これは公立小学校の約4.7倍にあたる金額です。この学費には授業料だけでなく、学校納付金、施設費、教材費、制服代、修学旅行費、課外活動費などが含まれています。また、入学時には別途入学金(約20~30万円程度)や制服代、寄付金などの初期費用も必要となります。6年間通う場合、総額で約1,000万円近くの費用が必要になると考えられています。
さらに、私立小学校では学校外活動費も大きな出費となります。多くの私立小学校では課外活動やクラブ活動が盛んであり、学外での習い事や塾に通う生徒も少なくありません。特に中学受験を見据えて塾に通わせる場合、年間で50万円~100万円の費用がかかることもあります。したがって、学費以外にも教育費全体を考慮する必要があります。
| 項目 | 私立小学校(年間) | 公立小学校(年間) |
|---|---|---|
| 授業料 | 536,232円 | 0円 |
| 学校納付金・施設費等 | 162,624円 | 8,113円 |
| 学用品費・実習材料費 | 49,932円 | 24,286円 |
| 学校給食費 | 45,139円 | 39,010円 |
| 通学関係費(交通費など) | 104,467円 | 20,460円 |
| 学校外活動費(習い事など) | 660,797円 | 247,582円 |
| 合計 | 1,666,949円 | 352,566円 |
このような学費を支払うために必要な世帯年収の目安は、一般的に1,200万円以上とされています。実際、私立小学校に通わせている家庭の約半数が年収1,200万円以上というデータがあります。(文部科学省)この年収であれば、学費だけでなく、習い事や塾、旅行など子どもの成長に必要な支出にも対応できるためです。一方で、年収600万円~1,000万円の家庭でも、家計のやりくり次第で私立小学校に通わせることは可能です。この場合、共働きで世帯年収を増やしたり、教育費を優先的に確保するために生活費を見直すなどの工夫が求められます。
また、学費の負担を軽減するための支援制度もあります。多くの私立小学校では、経済的な理由で学費の支払いが困難な家庭向けに奨学金や減免制度を設けています。これにより、世帯年収が比較的低くても私立小学校への進学が可能となるケースもあります。また、各自治体によっては私立小学校に通う家庭向けに補助金を支給する制度がある場合もあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。
一方で、私立小学校に通わせることにはデメリットもあります。学費負担が大きいことから、家計全体に圧迫が生じるリスクがあります。例えば、住宅ローンや老後資金など、他の大きな支出とのバランスを考慮しなければなりません。また、兄弟姉妹がいる場合、全員を私立に通わせるとなると負担はさらに大きくなります。
このように、私立小学校に通わせるためには、一定の世帯年収と経済的な準備が必要です。しかし、学費だけにとらわれず、家庭の教育方針や子どもの個性に合った学校選びをすることが重要です。将来的な支出も見据えた上で、無理のない範囲で計画を立て、家族全員が納得できる形で私立小学校への進学を検討しましょう。
共働き家庭におすすめな私立小学校の選び方を総括
この記事のポイントをまとめます。
- 共働き家庭でも通いやすい私立小学校の特徴を押さえる
- アフタースクールが充実している学校を選ぶと放課後も安心
- 給食制度が整っている学校はお弁当作りの負担を軽減できる
- PTA活動の負担が少ない学校は共働き家庭に適している
- 学校行事が平日だけでなく休日にも開催されると参加しやすい
- 通学の安全性が確保された学校は親も安心できる
- アフタースクールで宿題サポートがあると家庭学習の負担が減る
- シッターサービスや送迎付きアフタースクールを活用すると便利
- 夏休みや長期休暇中に学童やサマースクールがあると安心
- 学費や諸費用を事前に確認し家計に合う学校を選ぶ
- 共働き家庭向けの奨学金や補助制度の有無を確認する
- 小学校受験対策には家族でスケジュール管理を徹底する
- 面接では共働き家庭でも十分な教育環境を整えていることをアピール
- 通学に付き添いが必要な場合、安全なルートや緊急時対応を考慮する
- 共働き家庭に理解のある学校を選ぶことで両立がしやすくなる



