小学校受験において、絵画試験が出題される学校は少なくありません。特に難関校では、子どもの創造力や表現力、指示の理解力を測るために、独自の出題形式が採用されています。しかし、なぜ絵画が評価の対象となるのか、どのような問題が出題されるのか、具体的な対策方法はあるのかと疑問に思う方も多いでしょう。
本記事では、小学校受験で絵画が出る学校を詳しく紹介し、出題傾向や頻出のお題について解説します。また、効果的な教え方や練習方法、自宅でできる対策、絵画教室(東京・横浜エリア)での指導の特徴についても触れながら、試験に向けた準備のポイントをまとめました。さらに、家庭教師を活用するメリットや過去問の活用法についても解説し、合格を目指すための実践的なアプローチを紹介します。
小学校受験の絵画試験は、単なる絵の上手さを競うものではなく、子どもの発想力や観察力を試される重要な課題です。適切な準備を進めることで、試験本番でも自信を持って臨むことができるでしょう。
- 小学校受験で絵画が出る学校とその特徴
- 試験でよく出題されるお題や出題形式
- 自宅や絵画教室でできる効果的な対策方法
- 家庭教師や過去問を活用した受験対策のポイント
小学校受験で絵画が出る学校と特徴
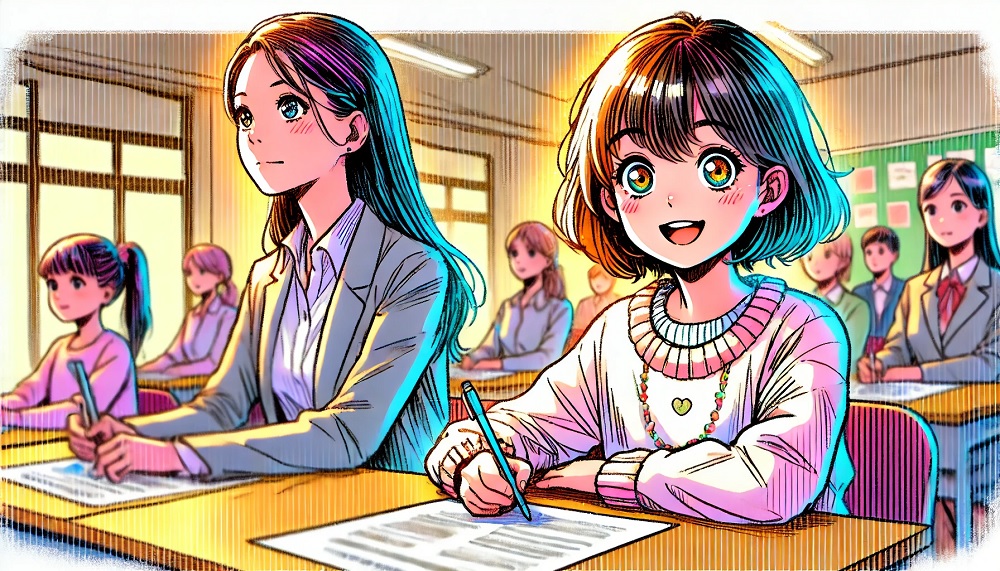
- お受験で絵画試験がある理由とは?
- 絵画が出題される代表的な私立小学校一覧
- 学校が求めるポイントと評価基準
- 試験の形式とよく出るお題
- 絵画問題と過去問の活用法
お受験で絵画試験がある理由とは?
小学校受験において、絵画試験を実施する学校は少なくありません。これは、子どもの創造力や表現力を測るための重要な手段として位置付けられているためです。では、なぜ絵画試験が必要とされるのでしょうか。
一つ目の理由として、子どもの思考力や想像力を確認できるという点が挙げられます。絵を描く行為には、単なる技術の上手下手だけでなく、物事をどのように捉え、どのように表現するかという思考の過程が含まれます。例えば、「家族と過ごした思い出の場面を描いてください」といった課題では、子どもがどの場面を選び、どんな構成で表現するかが問われます。このように、絵画試験を通じて子どもの内面や発想力を知ることができるのです。
次に、指示を理解し、正しく表現できるかを判断するためという理由があります。小学校の授業では、教師の指示を聞き、それに従って作業を進めることが求められます。絵画試験では、「○○を描きなさい」といった具体的な指示が与えられることが多く、それを的確に理解して表現できるかが評価のポイントになります。特に、慶應義塾幼稚舎や早稲田実業学校初等部などでは、ただ絵を描くだけでなく、工作を作り、それを使っている様子を描くといった複合的な課題も出されることがあります。これは、より高度な思考力や創造力を試すための工夫といえるでしょう。
さらに、協調性やコミュニケーション能力を確認する目的もあります。一部の学校では、個別の絵画課題だけでなく、複数の子どもが共同で一枚の絵を完成させる「共同絵画」の試験が行われることもあります。ここでは、お互いに相談しながら作業を進めることが求められ、協調性や他者と協力する力が評価されます。また、完成した絵について先生から質問を受ける場合もあり、その際にどのように説明するかによって、言語能力や自分の考えを伝える力も見られるのです。
このように、小学校受験の絵画試験は、単なる「絵の上手さ」を測るものではなく、子どもの思考力、想像力、指示の理解力、協調性、表現力などを総合的に評価するための重要な試験なのです。そのため、事前に適切な対策を行い、単なる絵の練習だけでなく、話し合いや説明の練習も含めて準備することが求められます。
絵画が出題される代表的な私立小学校一覧
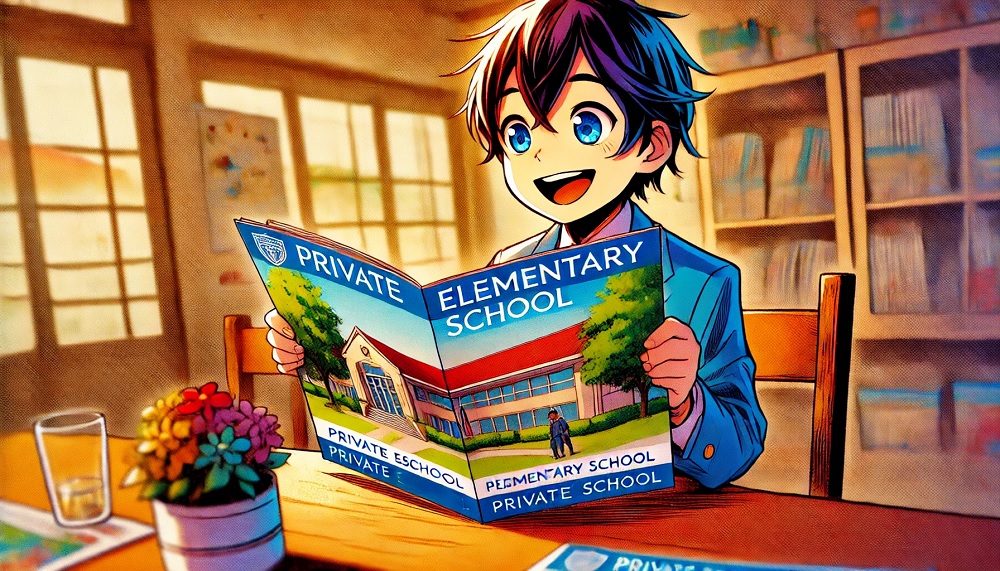
小学校受験において絵画試験を実施する学校は限られていますが、難関校を中心に一定数の学校で導入されています。以下に、代表的な私立小学校を紹介します。
慶應義塾幼稚舎
慶應義塾幼稚舎は、毎年絵画や工作を組み合わせた課題を出題しています。例えば、「自分で作った工作を使っている絵を描く」など、創造力や応用力を試される課題が特徴です。先生からの質問に答えながら作業を進める場面もあり、受け答えのスムーズさも評価のポイントとなります。
慶應義塾横浜初等部
幼稚舎と同様に、絵画試験が重視されています。特に、思考力や表現力を問うような課題が出されることが多く、単に与えられたテーマを描くだけでなく、自分なりのアイデアを加えることが求められます。
早稲田実業学校初等部
こちらも毎年絵画試験が出題される学校の一つです。「風邪をひいたお母さんに届けたいものを描く」など、特定の状況を設定し、その場面を表現することが求められます。単なる絵のスキルだけでなく、物語性や想像力が重要視される点が特徴です。
青山学院初等部
青山学院初等部では、過去に絵画試験が実施されており、自由な発想を重視する傾向があります。特に、色彩の使い方や構図の工夫など、個性を活かした表現が求められます。
学習院初等科
学習院初等科では、絵画の試験が行われることがあります。テーマに沿って自分の考えを表現する能力や、細部まで丁寧に描ける力が評価される傾向にあります。
雙葉小学校
雙葉小学校では、指示に従って絵を描くことが求められます。指示の理解力や構成力が問われるため、普段からさまざまなテーマで絵を描く練習をしておくことが重要です。
東京女学館小学校
東京女学館小学校の絵画試験では、物語性のある絵を描くことが求められることがあります。登場人物の動きや表情を豊かに表現することで、物語の世界観をしっかりと伝えることがポイントです。
森村学園初等部
森村学園では、子どもの自由な発想を活かせる絵画課題が出題されることがあります。特に、豊かな色彩表現や細かい描写ができることが評価の対象となる傾向にあります。
これらの学校では、単なる絵の技術以上に、創造力や発想力、指示を理解する力、協調性などが求められます。そのため、日頃から絵画の練習だけでなく、さまざまな体験を通じて感性を磨くことが大切です。
学校が求めるポイントと評価基準

小学校受験における絵画試験では、単に「絵が上手に描けるか」という点だけが評価されるわけではありません。むしろ、学校側は絵を通じて子どもの内面や思考のプロセスを見極めようとしています。そのため、評価基準は多岐にわたり、単なる技術力だけでなく、創造力や指示理解力、表現力など、さまざまな要素が含まれます。
まず、学校が重視するのは、子どもの創造力と発想力です。絵画試験では、「自分が宇宙に行ったら何をするか」や「未来の公園を想像して描いてみましょう」といった想像力を試すような課題が出されることがあります。このとき、ありきたりな内容を描くだけではなく、独自の視点やアイデアが表現できているかがポイントになります。たとえば、宇宙の絵を描く際に、単に星やロケットを描くだけでなく、「宇宙でピクニックをしている様子」や「宇宙人と遊んでいる様子」など、自分なりのストーリーを表現できると、より高い評価につながります。
次に、指示の理解力とそれを正しく表現できるかどうかも重要なポイントです。多くの学校では、単に自由に絵を描かせるのではなく、「○○の場面を描きましょう」「次の条件を満たして絵を描きなさい」といった形で具体的な指示が与えられます。これに対して、子どもが指示を正確に理解し、それに沿った内容を描けるかが試されます。特に、慶應義塾幼稚舎などの難関校では、「作った工作を使っている場面を描く」「先生の話を聞いて、その内容を絵にする」といった複雑な指示が出されることがあり、単なる絵のスキルだけでなく、理解力や応用力が求められます。
また、絵の構成力や表現力も評価基準の一つとなります。子どもがどのような視点で物事を捉え、それをどのように構成して絵に落とし込むかは、学校側にとって重要な観点です。例えば、家族でお出かけした思い出の絵を描く場合、単に人物を並べるのではなく、「誰がどの位置にいるのか」「背景はどう表現するのか」「どのような動作をしているのか」など、構図の工夫が見られるかがポイントになります。また、色使いや細部の描写にも個性が表れるため、全体のバランスや色彩感覚を総合的に評価する学校もあります。
さらに、試験中の態度やコミュニケーション能力も見られることがあります。特に、試験官が「これは何を描いたの?」と質問したときに、子どもが自信を持って説明できるかどうかが大切です。学校によっては、絵を描き終えた後に自分の作品について発表させるケースもあり、その際にどのように話をまとめ、相手に伝えられるかが評価の対象となることがあります。また、共同制作の課題が出される場合には、友達と相談しながら作業を進めることができるか、道具を譲り合って使えるかといった協調性も大きなポイントとなります。
このように、小学校受験の絵画試験は、単に「絵が上手に描けるか」ではなく、子どもの発想力や理解力、表現力、コミュニケーション能力などを総合的に判断するためのものです。したがって、試験対策をする際には、単に絵の技術を磨くだけでなく、さまざまなテーマに触れて発想を豊かにすることや、日常生活の中で物事を観察し、自分なりに考える習慣をつけることが重要になります。
試験の形式とよく出るお題

小学校受験の絵画試験では、学校によって出題形式が異なりますが、大きく分けて「自由画」「指示画」「共同制作」の三つの形式がよく見られます。それぞれに求められる力が異なり、事前にどのような対策を行うべきかを理解しておくことが重要です。
まず、「自由画」は、特定のテーマが与えられ、それに沿って自由に絵を描く形式です。「夏休みの思い出を描きましょう」「好きな動物を描いてみましょう」といった比較的オーソドックスなテーマが多く、子どもの発想力や表現力を評価する目的があります。自由画では、どのような構成で描くのか、色の使い方、登場人物や背景の描き込み方などがチェックされます。また、子どもが自分の経験や感情をどのように反映させているかもポイントになります。そのため、日常の出来事を振り返る習慣をつけ、スケッチブックに絵日記を描くなどの練習が有効です。
次に、「指示画」は、試験官から与えられた具体的な指示に従って描く課題です。「折り紙で作ったものを使って、それを活かした絵を描きなさい」「○○の道具を使っているところを描きなさい」など、一定の条件が設けられることが特徴です。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業学校初等部では、こうした指示画の出題が多く見られ、単なる描画力だけでなく、指示の理解力や応用力が求められます。たとえば、「お手伝いをしている様子を描く」という課題では、掃除や料理をしている場面を、適切な構図や表情で表現する必要があります。このタイプの試験では、細かい指示を聞き逃さず、それを正しく絵に反映する力が評価されます。
さらに、「共同制作」という試験形式もあります。これは複数の受験生が一つの作品を協力して仕上げるもので、絵を描くだけでなく、作業の進め方や協調性も試される試験です。「動物園の絵をみんなで完成させましょう」などのテーマがあり、道具の貸し借りやアイデアの共有が求められます。この場合、リーダーシップを発揮することも重要ですが、一方で他の子どもと調和しながら制作を進める柔軟性も評価されるポイントになります。
では、具体的にどのような「お題」がよく出るのかを見てみましょう。まず、「季節の行事」は定番のテーマです。「夏祭りの様子」「クリスマスの出来事」「お正月の家族団らん」など、子どもが実際に体験したことを描けるような内容が多く出題されます。この場合、描写の細かさだけでなく、その行事をどのように理解しているかも試されます。たとえば、七夕の絵を描く場合、単に笹と短冊を描くだけでなく、「願いごとを書いている自分」や「家族と一緒に楽しんでいる様子」など、情景をしっかり描けると高評価につながります。
また、「家族や友達との思い出」も頻出テーマです。「家族でピクニックに行った様子」「友達と遊んでいる場面」などが出されることがあり、ここでは家族や友人との関係性や感情表現が重視されます。「お母さんと料理をしている絵」などでは、楽しそうな表情や動作を意識して描くことが求められます。
さらに、「想像力を試すお題」も増えてきています。「未来の街はどんなところ?」「もしも動物と話せたら?」など、子どもの独創性を問う問題です。こうした問題では、どれだけユニークなアイデアを思いつくかが鍵になります。たとえば、未来の街を描く場合、単に高層ビルが並ぶ街並みを描くのではなく、「空飛ぶ自動車」や「水の上に浮かぶ家」など、子どもならではのユニークな発想が求められます。
このように、小学校受験の絵画試験は、形式やお題によって求められる力が異なります。日頃からさまざまなテーマで絵を描く習慣をつけることで、試験本番でも柔軟に対応できるようになります。
絵画問題と過去問の活用法

絵画試験の対策を進める上で、過去に出題された問題を活用することは非常に効果的です。特に、難関校では毎年似たようなテーマが出されることが多いため、過去問を分析し、どのような傾向があるのかを知ることが重要です。
たとえば、慶應義塾幼稚舎の過去問を見てみると、「自分が作った工作を使った絵」や「宇宙人と遊ぶ様子」など、想像力を活かすテーマが多く出題されています。一方、早稲田実業学校初等部では、「お母さんが風邪をひいたときに、自分ができること」など、身近な出来事をもとにした課題が多く見られます。このように、志望校ごとにどのような問題が出されるのかを把握し、傾向に沿った練習を行うことが大切です。
過去問を活用する際には、単に同じ絵を描くのではなく、「どういう力が求められているのか」を考えながら取り組むことが重要です。例えば、「お手伝いをしている様子を描く」という課題があった場合、「家の中での手伝いに限定されるのか?」「外での手伝いも含めて考えられるか?」など、さまざまな角度からテーマを深掘りしてみると、より柔軟な発想が生まれます。
また、過去問を使った練習では、時間を計って描くことも有効です。本番では制限時間内に描き終える必要があるため、普段から「20分以内に完成させる」といった時間制限を設けると、実践的な力が身につきます。特に、細かい部分にこだわりすぎて時間が足りなくなるケースも多いため、全体のバランスを見ながら効率よく描く練習をすることがポイントです。
さらに、描いた絵について親や先生と話し合うことも大切です。絵画試験では、試験官から「これは何を描いたの?」と質問されることがあるため、普段から「どうしてこの構図にしたの?」「どんな気持ちを込めたの?」と聞かれる習慣をつけることで、言葉で説明する力も養われます。
このように、過去問を活用することで、試験の傾向を知るだけでなく、時間管理や説明力の向上にもつながります。実際に描いてみることで課題が見えてくるため、できるだけ多くの過去問に取り組み、本番に向けた準備を整えていきましょう。
小学校受験で絵画が出る学校の対策と家庭での準備

- 絵画の教え方と効果的な練習方法
- 自宅でできる絵画対策
- 東京や横浜のおすすめ絵画教室
- 家庭教師を利用するメリットとは?
- 本番で慌てないための対策ポイント
絵画の教え方と効果的な練習方法
小学校受験に向けた絵画対策では、子どもにどのように絵を教えるかが重要になります。単に「上手に描く」ことを目指すのではなく、表現力や創造力を伸ばしながら、試験で求められるポイントを押さえることが大切です。そのため、教え方にはいくつかの工夫が必要になります。
まず、基本的な描画技術を身につけることから始めることが効果的です。幼児はまだ手の動きが未熟なため、いきなり細かい絵を描かせるのではなく、まずは丸や三角、四角などの基本的な形を描く練習をしましょう。例えば、「丸で顔を描こう」「三角を組み合わせて家を作ってみよう」といったシンプルな練習を繰り返すことで、少しずつ絵の構成を理解できるようになります。また、クレヨンや色鉛筆の持ち方を正しく指導することで、筆圧の調整や細かい線の描き分けができるようになります。
次に、想像力を育むためのトレーニングも重要です。絵画試験では、テーマに沿って自由に発想を広げる力が求められます。そのため、「もしも○○だったらどうする?」といった問いかけをしながら、子どもが自由に考えて描ける環境を作りましょう。例えば、「もしも空を飛べる動物がいたらどんな姿?」と質問してみると、子どもは自分なりの発想で絵を描こうとします。このような自由な創作活動を繰り返すことで、試験でも独自の表現ができるようになります。
また、描いた絵について会話することも大切なポイントです。絵画試験では、先生から「これは何を描いたの?」と質問されることがあります。その際に、子どもが自分の絵を説明できることが求められます。日頃から「この部分はどうしてこう描いたの?」「どんな気持ちで描いた?」と問いかける習慣をつけると、自然と説明力が向上します。
さらに、試験でよく出るテーマを意識した練習を取り入れることも効果的です。例えば、「家族の絵」「お手伝いの様子」「季節の行事」「友達と遊んでいる場面」などは、頻出のテーマとして知られています。これらを定期的に描かせることで、試験本番でもスムーズに対応できるようになります。また、試験では時間制限があるため、「20分以内に仕上げる」という練習をしておくと、実践的な力が身につきます。
こうした方法を組み合わせることで、絵画の表現力や創造力を伸ばしながら、試験に対応できる力を養うことができます。絵を教える際には、「楽しい」と感じることが最も重要なので、無理に修正をさせるのではなく、子どもの発想を尊重しながら指導することを心がけましょう。
自宅でできる絵画対策

小学校受験のための絵画対策は、必ずしも専門の絵画教室に通う必要はありません。自宅でも工夫次第で十分な対策を行うことが可能です。特に、時間の制約がある家庭や、費用を抑えたい場合には、自宅での練習が重要になります。
まず、日常生活の中で絵を描く習慣をつけることが基本になります。例えば、スケッチブックを用意し、「今日の出来事を描いてみよう」といった形で毎日短時間でも絵を描く習慣を作ることが大切です。また、「お手伝いをしたことを描いてみよう」「公園で遊んだことを絵にしてみよう」など、具体的なテーマを与えることで、試験対策にもつながります。
次に、過去問や想定問題を活用するのも効果的な方法です。小学校受験の絵画試験では、似たようなテーマが繰り返し出題されることが多いため、過去に出された問題を参考にしながら練習することで、試験での対応力を養うことができます。たとえば、「未来の街を描く」「自分が動物になったら何をする?」といった想像力を試す問題を出し、自分なりのアイデアを絵にする練習をしましょう。
また、絵を描く際の環境づくりも重要です。絵を描くことを楽しめるように、自由に使える画材を用意し、リラックスした雰囲気の中で取り組める環境を整えましょう。特に、クレヨンや色鉛筆、水彩絵の具など、さまざまな道具を使うことで、表現の幅が広がります。
さらに、親子で一緒に取り組むことも有効です。「一緒に動物を描いてみよう」「お互いの顔を描いてみよう」といった共同作業を取り入れることで、子どもの興味を引き出しやすくなります。親が一緒に絵を描くことで、子どもは安心感を持ち、積極的に取り組むようになります。
このように、自宅でも工夫次第で十分な絵画対策が可能です。特に、小学校受験においては、絵の技術だけでなく、発想力や表現力も重視されるため、日常の中で楽しく絵を描く習慣をつけることが重要になります。
東京や横浜のおすすめ絵画教室

小学校受験の絵画対策として、専門の絵画教室に通うことも一つの選択肢です。特に、東京や横浜には、受験対策に特化した絵画教室が多く存在し、それぞれの学校の傾向に合わせた指導を受けることができます。
東京でおすすめの絵画教室として、アトリエひまわり(恵比寿・広尾)が挙げられます。この教室は、慶應義塾幼稚舎の受験対策に特化しており、マンツーマン指導が特徴です。過去の出題傾向を分析しながら、個別のレベルに合わせたカリキュラムが組まれているため、確実に力を伸ばすことができます。
また、アトリエ・ミオス(川崎・元住吉)も人気のある絵画教室の一つです。こちらは、絵画だけでなく、立体制作や造形を取り入れた授業があり、幅広い表現方法を学ぶことができます。
横浜エリアでは、アトリエセラセラ(横浜雙葉・森村学園受験対応)が評判の良い教室の一つです。受験生向けの少人数クラスがあり、個別指導も充実しているため、初心者でも安心して通うことができます。
これらの教室では、受験に必要なスキルを重点的に指導してくれるため、本番に向けた実践的な対策が可能になります。自宅学習だけでは不安な場合や、専門的な指導を受けたい場合は、こうした教室の活用を検討してみるのも良いでしょう。
家庭教師を利用するメリットとは?

小学校受験の絵画対策において、家庭教師を利用することには多くのメリットがあります。特に、個別指導のため子どもの成長スピードに合わせた学習ができる点は、大きな魅力といえるでしょう。
まず、子どものペースに合わせた指導ができるという点が挙げられます。集団指導の絵画教室では、クラス全体のレベルに合わせて授業が進められるため、子どもがついていけなくなることもあります。一方で、家庭教師であれば、子どもの得意・不得意に応じた指導が可能です。例えば、細かい描写が苦手な子どもには、線を描く練習から始めたり、色の塗り方を丁寧に指導したりと、個々の課題に対応したレッスンができます。また、指示理解が苦手な場合には、試験で出される課題を想定しながら、「このお題では何を描けばいいのか?」と考えさせる訓練を行うこともできます。
次に、家庭の都合に合わせたスケジュール調整がしやすいというメリットもあります。絵画教室に通う場合、決められた曜日や時間に合わせる必要があり、他の習い事との兼ね合いが難しくなることがあります。しかし、家庭教師であれば、親のスケジュールに合わせて指導日を決められるため、効率的に受験準備を進めることができます。また、送迎の手間がなく、自宅で指導を受けられることも、共働き家庭や忙しい親にとっては大きな利点となります。
さらに、受験対策に特化した指導が受けられる点も家庭教師の強みです。一般の絵画教室では、創造力や表現力を伸ばすことに重点を置いているところが多いですが、小学校受験では「試験で求められるスキル」を身につけることが重要になります。例えば、慶應義塾幼稚舎や早稲田実業学校初等部のように、工作と絵画を組み合わせた課題を出題する学校では、単なる絵の練習だけでは対応できません。家庭教師ならば、志望校の出題傾向を分析し、試験形式に沿った課題を繰り返し練習できるため、本番に向けた実践的な力を養うことができます。
また、講師との対話を通じて表現力が向上することも期待できます。絵画試験では、試験官から「これは何を描いたの?」と質問されることがあり、その際に自分の絵について説明する力が求められます。家庭教師のレッスンでは、子どもが描いた作品について講師と対話しながら、自分の考えを整理し、伝える練習ができます。こうしたやり取りを積み重ねることで、受験本番でも自信を持って受け答えができるようになります。
一方で、家庭教師を利用する際には、講師の選び方が重要になります。指導経験が豊富で、受験に特化した知識を持っているかどうかを確認することが大切です。また、子どもとの相性も重要な要素となるため、体験授業を受けてみるのも良い方法です。
このように、家庭教師を利用することで、子どもに合った指導を受けることができ、受験に必要なスキルを効率的に伸ばすことができます。絵画試験に不安がある場合は、こうした個別指導を検討するのも一つの選択肢といえるでしょう。
本番で慌てないための対策ポイント
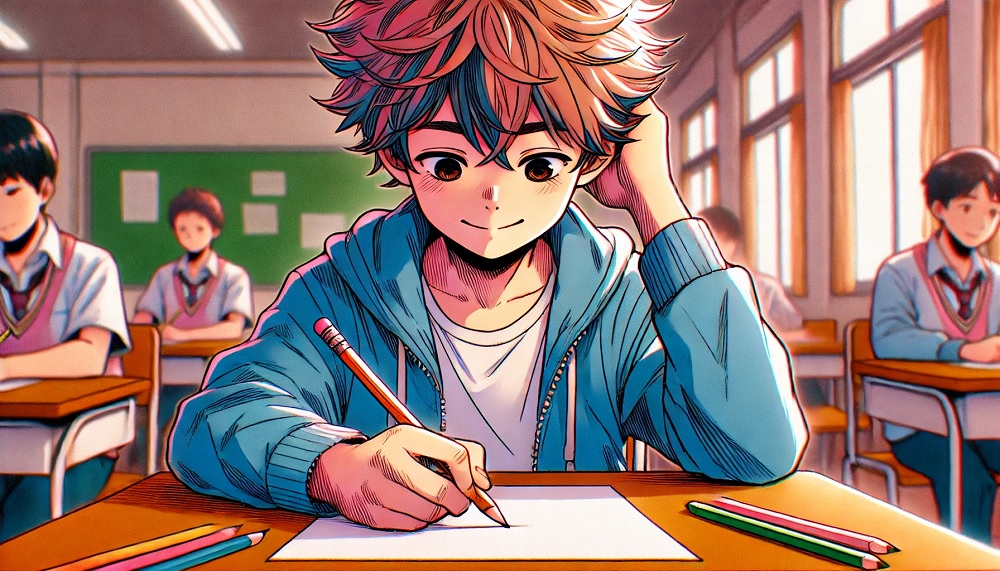
小学校受験の絵画試験では、本番の緊張感の中でいかに普段通りの力を発揮できるかが重要になります。特に、限られた時間の中で課題を完成させなければならないため、事前に十分な準備をしておくことが大切です。
まず、時間配分を意識した練習を行うことが重要です。試験では、おおよそ20~30分の時間制限の中で課題を仕上げる必要があり、時間をかけすぎると完成しない可能性があります。そのため、普段の練習でも「〇〇分以内に描く」という時間設定をし、制限時間内に描き切る力を養うことが必要です。例えば、最初の5分で構図を決め、次の10分で大まかな形を描き、残りの時間で細かい部分を仕上げるといったペース配分を意識すると、本番でも焦らず取り組むことができます。
次に、試験環境に慣れるための模擬試験を行うことも効果的です。実際の試験では、慣れない場所で、多くの受験生と一緒に試験を受けるため、普段と違う環境に戸惑うことがあります。そのため、自宅でも机の配置を変えたり、違う場所で絵を描いたりすることで、本番の環境変化に慣れておくと良いでしょう。また、模擬試験を行うことで、時間配分の感覚を身につけることもできます。
さらに、試験でよく出るテーマを事前に想定し、練習しておくことも大切です。例えば、「家族と一緒に過ごした楽しい思い出」「お手伝いをしている様子」「季節のイベント」などは、頻繁に出題されるテーマです。事前に何度か同じテーマで描いておくことで、本番でお題が出された際にすぐに取りかかることができ、時間を無駄にしなくて済みます。
また、試験中のトラブルに対する対応力を養うことも忘れてはいけません。例えば、クレヨンが折れてしまったり、絵の具が思ったように使えなかったりすることも考えられます。このような場合に焦らず対応できるよう、普段から「別の色で代用する」「違う描き方を試してみる」などの方法を考えながら描く習慣をつけておくと安心です。
最後に、試験前のリラックス方法を身につけておくことも大切です。緊張しやすい子どもは、本番で普段の力を発揮できないことがあります。そのため、試験前に深呼吸をしたり、手を軽く動かしてリラックスする方法を教えておくと良いでしょう。また、試験前に「落ち着いて描けば大丈夫だよ」と声をかけてあげることで、安心感を持たせることができます。
このように、事前にしっかりと準備をしておくことで、本番でも焦らず落ち着いて試験に臨むことができます。普段の練習の中で、時間配分や環境への適応、トラブル対応などを意識しながら取り組むことが、合格への鍵となるでしょう。
小学校受験で絵画が出る学校の特徴と対策を総括
この記事のポイントをまとめます。
- 小学校受験で絵画試験を実施する学校は、創造力や表現力を重視している
- 絵画試験では、子どもの思考力や指示理解力も評価される
- 慶應義塾幼稚舎や早稲田実業学校初等部などでは、複合的な課題が出題される
- 共同制作の試験では、協調性やコミュニケーション能力が求められる
- 試験の形式は「自由画」「指示画」「共同制作」の3種類が多い
- 受験絵画では、季節の行事や家族の思い出などのテーマが頻出する
- 想像力を試す問題も増えており、独自の発想が評価のポイントとなる
- 過去問を活用することで、出題傾向を把握し対策が立てやすくなる
- 絵画試験の対策には、日常の出来事を描く習慣をつけることが有効
- 自宅での対策として、時間を測りながら描く練習をすると効果的
- 東京や横浜には、小学校受験に特化した絵画教室が多く存在する
- 家庭教師を利用すれば、個別指導で受験対策を強化できる
- 本番で慌てないために、模擬試験や環境を変えた練習を取り入れる
- 絵画試験では、完成度だけでなく、説明力や発想の豊かさも評価される
- 日頃から親子で絵を通じた会話を増やし、表現力を高めることが重要



